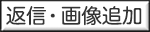|
| | | |

|
53669: コナラ属をナラ属と呼ぶことについて
|
このきなんのき所長 7月 6日(日) 15:20
|
|
|
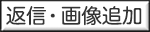 |
|
樹木好きな皆さんにご意見を伺いたくて投稿します。
ブナ科コナラ属の名称について、サクラ属やツツジ属などと異なり、コナラ属だけが総称ではなく固有の種名が属の和名になっていることを以前から疑問に思っており、「ナラ属」という呼称を私の図鑑で提案したいと思っています。属の和名は、内包する種の総称であることが望ましいからです。
これについて、賛否の意見があれば聞かせていただけませんか。
|
ガリー 7月 6日(日) 16:10 そもそも
「コナラ属」
という命名になった経緯がわからないのでなんとも言えません。
その経緯がおわかりであれば教えていただきたい。
個人的にはコナラ属でも気になりません。わざわざ変更することの方が煩わしいとも感じます。 |
sanpo 7月 6日(日) 19:33 所長様、皆様、こんばんは。
ブナ科の属について、今まで深く考えたことはなかったのですが、言われてみれば、クリ属はクリ1種のみ、ブナ属、シイノキ属、マテバシイ属は2種ずつなのに対して、コナラ属は落葉あり常緑ありの20種ほどの大所帯です。
しかも、所長さんがおっしゃるように、コナラという種名が属名になっているのも、確かに違和感がありますね。同時に、コナラ属だけ大雑把なのではと思ってしまいました。
所長さんは既にご存知かと思いますが、下記のようなQ &Aがありました。
属の命名は慣習のようなものなのでしょうか?
https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=4923 |
あかね雲 7月 6日(日) 21:28 所長さま 皆さま sanpoさま こんばんは
ナラノキという木を見たこと無いので「ナラノキってどういう木」と夫に尋ねました
この地の里山の多くの先代の人たちは落葉樹の林を利用を生業としていました 夫もそれなりにこの地に植生の木のいろいろは広く浅くですが知っているので尋ねました
すると「ナラノキという木は無い この地でナラノキといえばコナラのこと ミズナラや交雑のナラ類やクヌギもあるけどナラノキといえばコナラのことだよ」と言いました
sanpoさんの紹介されたサイトにも『代表的な種の和名を使っています ナラ ナラノキという種はありません』と書かれてあり納得いたしました
そしてsanpoさんの仰るようにコナラ属は落葉樹と常緑樹が似ていないものも同じ属というのも大雑把で違和感ありますね
ナラ属に代えるのに賛成かコナラ属のままで良いか どちらかに賛成の判断ができませんのに僭越な意見を失礼いたしました |
sanpo 7月 7日(月) 10:16 皆様、おはようございます。
「コナラ属」という属名につきましては、確かに突っ込みどころが多く、どうしてこうなったのか疑問に思います。
その上で、所長さんの新しい図鑑で「ナラ属」を採用されることへの賛否を問われるなら、現時点では、私は「否」です。図鑑の生命線である信頼性に、少しでも疑義が差し挟まれることがあってはならないと思うからです。
属名に関する問題提起は、然るべき学会で行われるのが最善ではないでしょうか?
失礼の段は、お許し願います。
あかね雲さん
夫に先立たれた身として、ご夫婦の素敵な会話が羨ましく思いました。 |
このきなんのき所長  7月 7日(月) 11:10 7月 7日(月) 11:10 皆さんご意見ありがとうございます。
コナラ属のままでいい、というご意見も多いようですね。
sanpoさんが記されたURLに書かれているように、コナラを属の代表種として選んだのでしょうが、その名付けた方はむしろ例外で、サクラ属、ツツジ属、ヤナギ属、キイチゴ属、カエデ属のように、種名ではなく総称名で属の和名を名付けるのが大半です。
これらを、ヤマツツジ属、シダレヤナギ属、モミジイチゴ属、イロハモミジ属などと呼ぶのはおかしいでしょう? コナラ属だけがその状態です。
クマシデ属、という名称も以前は使われていましたが、最近はシデ属という呼称が定着しています。
種名が不明のサクラの木があった場合に、「サクラ」「サクラの一種」「サクラ類」のように属名を使って呼べば、総称にもなるので間違いにはなりません。
ところがコナラ属の場合のみ、「コナラ」「コナラの一種」「コナラ類」と呼ぶと、おかしなことになります。ですから、他の属名と基準を揃えて、総称に適した属の和名を提案したいと思っていますが、いかがでしょう? |
たろ 7月 7日(月) 14:51 本筋から外れるのですが、いい機会なので教えてください
学名は命名規約がある一方、和名(標準和名、地方名)は、なにやら命名者の思い入れだけで決まるようですね
(納得できない標準和名が山ほどあります)
だとすれば、学名の変更は難しくても、(混乱や周知性を無視すれば)和名を変えることは可能とは考えます。
そこで質問ですが、学名の属名を替えないままで、それに対応している日本語の属名の変更は可能なのでしょうか? |
このきなんのき所長  7月 7日(月) 19:06 7月 7日(月) 19:06 たろさんご指摘のように、和名には規約やルールはありません。よって、標準和名、というものも植物では定義されていないはずです。
なので、学者や命名者が和名を決めても普及しないケースも多々あるし、園芸業者がつけた呼称が定着するケースもあります。
属の学名はそのままに、対応する属の和名を変えて提案することは可能でしょうが、分類を定義するのは分類学者の専門領域なので、その和名を学界の外から勝手に提案すると、反発があるのかなと感じています。
ちなみに分類学者の間では、いろんな人がいろんな呼称を提案しています。たとえばAPG分類で誕生したサカキ科は、ペンタフィラクス科、モッコク科、サカキ科が使われましたが、サカキ科で定着した印象があります。 |
sanpo 7月 7日(月) 23:31 皆様、こんばんは。
どうやら、私は、樹木の学名や属、標準和名の命名について、何もわかっていないことに、やっと気づき始めています。
こういうものは全て、学会などしかるべきところで定めたものと思い込んでいたために、学校のテストで、例えば「クヌギは何科何属ですか?」という問題があった場合に、「ブナ科ナラ属」と書かれた図鑑で覚えた生徒は間違いとされてしまうという単純な発想でした。済みません。
業者による園芸種の命名が定着して結果オーライという世界であれば、多くの図鑑を出版された所長さんなら、なおのこと、よりふさわしい属名を提案される適任者と思われます。
というわけで、前言を撤回し、「ナラ属」という呼称を所長さんの図鑑で提案されることに「賛成」に乗り換えます。 |
K-ichi 7月 8日(火) 04:11 >園芸業者がつけた呼称が定着するケースもあります。
クレマチスとかシンビジュームとかハイビスカスとかでしょうか。
|
あかね雲 7月 8日(火) 10:54 所長さま 皆さま おはようございます
身近な馴染み深いコナラ属のことを学び直すことができました
コナラ属に落葉樹と常緑樹が一緒なのは古代はドングリが主食でありそのことからドングリが生る木を一属にということで理解しましたしました
クリはクリ属なのはドングリでは無いからでしょうか
コナラ属をナラ属に変更という 族への所長さまの想いがよく解り小さな一票ですが賛成いたします
sanpoさんもご主人さまとの想い出を大切にされているのでしょう
この地に住んで夫と樹木のいろいろな話しができるのは嬉しいことですね
ありがとうございます |
通行人C 7月 8日(火) 13:22 皆さん、こんにちは。
所長さんのご説は一理あると思いますが、少々疑念もあります。
「ナラ」と云う呼称が、「サクラ」や「モミジ」のように一般的に使われているかという点です。
私だけかもしれませんが、コナラは、西日本の暖温帯に住む者にも身近な存在で、「コナラの仲間」と聞けば直ぐにクヌギやカシワから、アラカシやシラカシの樫類までも連想できるのですが、「ナラ(楢)の仲間」にはあまりなじみがなく、ミズナラやレッドオークなど北方系の樹種で、ウヰスキー樽や北欧家具のイメージが強く、樫類迄はパッと浮かんできません。
「コナラ属」が定着しているのは、そういう一面があるのではと考えています。
「種名ではなく総称名で属の和名を名付けるのが大半」という所長さんのお考えには反しますが、属の和名は代表する種名が用いられることも多いように思います。
サクラ、カエデ、ヤナギ、キイチゴ、ツツジ、など総称名を属名にしているのは、古来から日本人になじみが深く、園芸種も多く、古くから総称が用いられていた樹種の集団があったからではないでしょうか。
古くからの総称が無かった「ウメ」や「モモ」はスモモ属(Prunus)が使われていますね。
逆に言えば、和名の種名の○○ザクラ、○○カエデ、○○ヤナギなどは、総称があったから名付けられたとも考えられます。
古くからの総称はあったけれども、落葉樹類には「楢」、常緑樹類には「樫」が使われていた「現コナラ属」を「ナラ属」にひっくるめてしまうのは無理があるように感じます。 |
sanpo 7月 8日(火) 17:20 皆様、こんにちは。
今回、素人なりにコナラ属について考える機会をいただき、常緑樹も落葉樹も“十把一絡げ”と思ってしまいましたが、通行人Cさんがおっしゃることを踏まえて、落葉樹をナラ属、常緑樹をカシ属と分ければ、スッキリするのではないかと思えてきました。
訳もわからずお邪魔して、大変失礼いたしました。 |
K-ichi 7月 8日(火) 18:44 >落葉樹をナラ属、常緑樹をカシ属と分ければ、スッキリする
世界標準の学名の分類にも関わる話で常緑か否かで属を分けろ、というのは乱暴すぎでは。
|
あかね雲 7月 8日(火) 20:34 再々のお邪魔をさせていただきます
先の投稿ではコナラ属をナラ属にということに大賛成ではなく小さく賛成しました
何となく残念さを拭えないからでした
やはり最初の投稿通り ナラ ナラノキ という木は日本には無くナラノキと言えばコナラと言われていること
コナラ属には落葉樹も常緑樹も共にドングリが生る木として同類とするコナラ属の意味を尊重したいと思いました
ナラという日本に無い木を日本の木の属名に相応しいかという疑問も残りました
いろいろ意見を申し上げて失礼いたしました |
このきなんのき所長  7月 8日(火) 22:31 7月 8日(火) 22:31 いろいろご意見ありがとうございます。
ナラという総称は昔から使われていますし、皆さん「コナラ」に馴染みが強いのは、コナラ属という名称が古くから図鑑で使われてきたのと、みなさんがコナラとカシが多い照葉樹林帯に住んでおられることもあるでしょう。
ちなみに、コナラ属のうち、落葉樹はコナラ亜属、常緑樹はアカガシ亜属という下位の分類群に分類されます。ただし、ウバメガシだけは例外で、常緑樹ですがコナラ亜属に分類されます。どんぐりの殻斗がコナラと同じ網目模様ですね。
ナラ属かカシ属かカシナラ属かコナラ属か、などを十分議論したのではなく、最初に著名な学者が「コナラ属」を使ったので、それがそのまま継承されてきたと推測しています。
故に、しっかり勉強してきた人ほど、sanpoさん仰るテスト的な回答である「コナラ属」を変更することに抵抗をもつのは理解できるのですが、僕はこれから植物を学ぶ若い人たちにわかりやすく伝えることを最優先に考えています。
通行人Cさんが仰る「属の和名は代表する種名が用いられることも多い」という具体例を5個ぐらい教えてもらえますか? 総称があるにも関わらず、代表種の種名が属名に使われているケースは、日本の木本類に関してはなかなか見当たらないです。 |
通行人C 7月 9日(水) 01:35 こんばんは。
所長さんに教えるなんておこがましい限りですが、ご指名により「属の和名は代表する種名が用いられている」例を思いつくまま挙げてみます。
クスノキ科クロモジ属、バラ科シモツケ属、モチノキ科モチノキ属、モクセイ科トネリコ属、ミズキ科ミズキ属、ガマズミ科ガマズミ属、ツツジ科スノキ属、スイカズラ科スイカズラ属、などです。
先に挙げたスモモ属は、ウメ、モモ、アンズなど代表する種の候補が多くて英名がプルーンのスモモが選ばれた例ではないでしょうか。
「総称があるにも関わらず、代表種の種名が属名に使われているケース」ですが、総称は「カキ(柿)」だが属名はカキノキ属の例はどうでしょうね(こだわり過ぎかな?)
書きながら思ったのですが、ヒノキ属のヒノキ、リンゴ属のリンゴ、イチジク属のイチジク、サンショウ属のサンショウ、などは、誰もが知っているような名称で、改良された品種も多いですが、種として他に似通ったものが無いので、総称ではないですよね? |
このきなんのき所長  7月 9日(水) 13:53 7月 9日(水) 13:53 通行人Cさん、ありがとうございます。
挙げられた例のほとんどは、総称名とも言えますよね。
クロモジは、ケクロモジ、ヒメクロモジなどの総称とも言えるし、トネリコも、シマトネリコ、ツクシトネリコ、セイヨウトネリコ、アメリカトネリコなどの総称と言えます。
カキノキは、総称なら確かにカキ、とすべきかもしれませんが、まあ違和感は感じないです。ヒノキ、リンゴ、サンショウもどれも総称として使えます。セイヨウヒノキ、ヒメリンゴ、カラスザンショウなどの同属の別種が多数あるからです。イチジクだけは、同属他種には「〜イヌビワ」の名がつく種が大半で、やや例外ですね。
ただ、コナラ属だけは、「〜コナラ」という別種は基本的にないので、総称のナラがあるのに、固有の種名が使われている唯一の例外と言えると思っています。
このような例が他にあるなら、知りたいのです。 |
たろ 7月 9日(水) 16:44 再度の投稿で失礼します。
当初感じたのは『なぜいまさら?』ということでした。
それはあたかも、APG体系により分類を見直す戸惑いに似たものでした。
要は、それまでの自分の慣れ親しんだ和名・知見を修正しなけれなならないことへの困惑とでもいえます。
しかし、所長の思いは『これから植物を学ぶ若い人たちにわかりやすく伝えることを最優先に』とのこと。
まさに 目から鱗の思いです。
単に和名を替えるということではなく、学名の属名に対応する和名の変更は分類学者からの反発は必至との所長の見解。
困難さが予想されますが、所長の図鑑によりそのことが実現できたらと思うとワクワクします。 |
このきなんのき所長  7月13日(日) 00:03 7月13日(日) 00:03 たろさん、コメントありがとうございます。
危機的な森林生態系の崩壊、里山の荒廃、地球環境問題を抱えている現代だからこそ、属和名に限らず、多くの若い人が分かりやすく植物や自然を学べることを第一義に、今後も務めていきたいと思います。
なお、今回の図鑑では「ナラ属」はすぐに使用せずに、コラム内でナラ属と呼ぶことを提案するにとどめることにしました。秋までに発売できると思います。
他の皆さんもありがとうございました。 |
|
|
|
| |
| | |
|
|
|