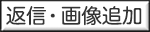|
| | | |

|
53747: ���̖͉��ł��傤
|
�ؔV�� 9�� 2��(��) 16:06
|
|
|
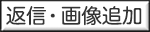 |
|
���N�O�ɂ�������ł��q�˂��܂������[���ł�����킪����ł��Ă��܂���B
�W���P�O�O�����̃X�M�̐A�ётő��Ɉ�{�P�ƁA�����R�u��ł��̌���ώ@���Ă��܂����قƂ�Ǒ傫���Ȃ炸�A�Ԃ��炫�܂���B
�~�G���قƂ�Ǐ�ʼn��t������������܂��B�������t��ɂ͈�x���ׂĂ̗t�͗�����悤�ł��B
�ʐ^���S���f�o���܂�.
�悸�t�}�̗l�q
|

�ؔV�� 9�� 2��(��) 16:19 �O�e�̎����u�R�u�v�͂R���̌��B
������}�t�B�}�����ɂႮ�ɂႵ�Ă��܂����c�����ł͂���܂���B
���}�̕��u�t�g�v�łȂ��u�x�v���J��Ԃ����߁A���ɂ���Č����܂� |

�ؔV�� 9�� 2��(��) 16:28 ����͗t�łőΐ��B�傫�ȗt�͒����W�Z���`���炢�B�傫�ȗt�̎�O�i�����j�ɏ����ȗt�̑�����܂����̕����̎}�͒�����B
�t�̂Ȃ����ł̎}�̕���́u�x�v�܂��́u���v��B
���̕ӂ����̖̓����Ǝv���܂��B |

�ؔV�� 9�� 2��(��) 16:35 ����͊��ł��B�����R�Z���`���炢�B
���Ȃ�����̂���Ǝv���܂����A�摜�������Ă݂Ă��A
�J�W�m�L�A�V�^�L�\�E�A�u�[�Q���r���A�E�O���O��
�ȂǁA�����̂�����������܂���B
��낵�����肢���܂� |
������ 9�� 2��(��) 17:34 �ΐ��t���őS���A�t���͒Z���A�喬�͗t���œ˂��o�Ă���悤�Ɋς��܂��B
����ɉ����̔�ڂ��ς��܂��B
����̃��N�Z�C�ȃI�I�o�C�{�^�����ɋ����܂��B
|
�Ԃ���  9�� 3��(��) 11:07 9�� 3��(��) 11:07 �S�̗̂l�q��������܂��A�}�̏o�����i�����j���}�̂悤�Ɍ����邱�ƁA�傫�ȗt�Ə����ȗt���ɂȂ��Ă���i�����ȗt�͗�������މ������肷�邱�Ƃ�����j���ƁA�h�炵�����̂���������Ȃ����ƂȂǂ���A�A�J�l�ȃA���h�I�V���̃W���Y�l�m�L�ɋ߂����Ǝv���̂ł����A�W���Y�l�m�L�͂܂��������Ƃ��Ȃ��̂Ŏ��M�͂���܂���B�W���Y�l�m�L�̕��z�͖{�B�i�ߋE�n���Ȑ��j�A�l���A��B�ŁA�H�ɐ�����悤�ł��B
�A�J�l�ȃA���h�I�V���͓��{�ɂP�P�핪�z����悤�ł����A�}�ӂɂ͂��̓��̐��킵���f�ڂ���Ă��Ȃ��āA���ׂ�̂͂��Ȃ����ł��B�W���Y�l�m�L�͏�������̒����u��������E���̗t�vP�U�T�X�Ɍf�ڂ���Ă��܂����A�h�͂قƂ�ǂȂ��������Ă��Z���Ə�����Ă��܂��B���[�y�Ō��Ȃ��ƕ����������m��܂���ˁB |
�Ԃ���  9�� 3��(��) 20:08 9�� 3��(��) 20:08 �u�傫�ȗt�Ə����ȗt���ɂȂ��Ă���v�͊ԈႢ�ŁA�u�傫�ȗt�̑Ə����ȗt�i���ɂ��Џ�ɂȂ�j�̑��P�̃��j�b�g�ɂȂ��Ă���v�ɕύX���܂��B
�ǐL�ł��B���q�˂̓W���Y�l�m�L�̗t���Ƃ͏����Ⴄ�悤�Ȃ̂ŁA���������Ē����܂��B
�����������Đ\����܂��A�p�X���[�h���Ⴄ�Əo�č폜�o���܂���B
|

�ؔV�� 9�� 4��(��) 00:18 �����悳��@�Ԏ����x���Ȃ肷�݂܂���B
�I�I�o�C�{�^�͖����ł����A���������t�ł͂���܂��B
�u����v�ɒ��ڂ��܂����B���̖͏��߂ɏ������悤�Ɍ��~���ɓ����Ă����ꂢ�ȗ̗t���c��A����Ǝv���Ǐt��ɂ͂�������S���̗t���͂ꗎ���܂��B�t�̌��������t���炵�������t�ł��B
�Ԃ�������R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���Ȃ������ڂ��ꂽ�}�̕���`��A�܂��ΐ��̗t�̑̉��ɏ����ȗt�̑����E�E�E���������̖̓����ł��B
���̌`���ɂ��Ď����A���h�I�V���Ɏ��Ă���Ǝv���܂��B
���̖̂���R�ɂ̓A���h�I�V��I�I�A���h�I�V�i�j�Z�W���Y�l�m�L�j���U�݂��悭���Ă��܂����A�A���h�I�V����肸���Ƒ傫�����L�ȗt�ŗ��t�����̔����t�ł��B
���̎R�ŎB�����I�I�A���h�I�V��\��܂��B���}�̕���⏬���ȗt�̑��킩��Ǝv���܂�
|

�ؔV�� 9�� 4��(��) 00:26 �����ꖇ�A����̓A���h�I�V�ł��B�t�����`�Ńg�Q�͒����ł��B
�O�f�̃I�I�A���h�I�V�͗t�̒����͂T�Z���`�قǂ���܂����g�Q�͏����߂ł��B
�A���h�I�V���͏�Ńo���o�����������t�ł��B
����̖A�A���h�I�V���Ɨގ��_������܂����A�q�m�L���X�M�̐A�щ��ɂP�{�����Ɨ����Ă��܂��B�Ȃ�̖��킩�炸�Y��ł��܂��B |

���E�A�� 9�� 4��(��) 02:39 �����́B
�����悳��̉]��ꂽ�I�I�o�C�{�^�̉\���͂���Ǝv���܂��B
����̓I�I�o�C�{�^�̋ߎ���̃��i�M�C�{�^�ł��B
�}��Y��������J��Ԃ����ɂ���Ă���l�q�A
�z�~����t�������܂��B |

���E�A�� 9�� 4��(��) 02:47 ���i�M�C�{�^�̗t�A����̗l�q�ł��B
���i�M�C�{�^�͂�����̒n�悩��O��܂��̂ŁA
����Ȃ���A���Q�l�܂ŁB |
�ؔV�� 9�� 4��(��) 23:23 ���E�A������@�R�����g���肪�Ƃ��������܂�
�����̎R�[�͂Ȃ�̂��߂��O������A�����ڐA���ꂽ�Ǝv������̂��F�X�����܂��B����̖����z��O����̂��́A�܂��͊O����������֎��������Ƃ͏\���l�����܂��B
�C�{�^�m�L���Ɋ܂܂���͑����A��Ύ��A����Ύ��A���t���̎킪���肻���ŁA����ɑ�����킩������܂���ˁB
|
|
|
|
| |
| | |
|
|
|